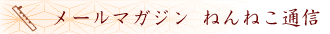

タイトル:ねんねこ通信40号
日付:2009/10/27(火)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ねんねこ通信 40号 2009.10 http://komoriuta.cside.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎目次
●ネーミング
●山梨県の子守唄
●コラム−上杉鷹山(うえすぎようざん)
●編集後記
============================================================================
◆ネーミング
球根類の春の準備を始めました。早春に咲く水仙には多くの種類があります。先日
インターネットで見つけた「金の鈴」という名の水仙を購入しました。画面で見ると
その名の通りの花形で、そこに書かれていたコメントにも惹かれたのです。
「花風水で金運アップ」です。花を楽しみながら金運アップが叶えられるとしたら
・・、と思い、つい買ってしまいました。人の心理を巧みに読んだネーミングです。
花でしたら、例え見本と少しくらい違っていても「こんなものか」で済ますことが
出来ますが、国の政治では許されることではありません。耳障りのいい言葉に、内容
が誤魔化されてしまわないよう、しっかりと見張っていかなければなりません。選挙
で選んだ責任もあるのです。
============================================================================
◆山梨県の子守唄
南巨麗郡早川町奈良田(県の南西に位置する)で採歌された子守唄は、この地区だ
けでしか唄われていなかったと書かれていました。(日本わらべ歌全集11巻)
奈良田の子守唄
・よいよいよお よいよいよ
しょんがいばんばあは 焼き餅好きで
ゆんべ九つ けさ七つ
一つ残して たもとにこいて(入れて)
馬に乗るとて うちょうといた(落としてしまった)
よお よいよいよ
奈良田平で 寒いとかどこだ
日影草里(ひかげぞうり)と へざかあば
よいよいよお よいよいよ
・よお よいよいよ
しょんがいばんばあ 焼き餅好きで
ゆんべ九つ けさ七つ
一つ残して たんぼ(袂)に入れて
馬に乗るとて うちょうといた
よお よいよいよ
うらが家のおぼこを 誰がかまった
だれもかまのに お泣きゃるか
よお よいよいよ
・奈良田平で 寒いとこどこだ
日影草里と へざかあば
しょうがいばんばは 焼餅好きで
ゆんべ九つ けさ七つ
一つ残して たもとに入れて
馬に乗るとて うちょうといた
なんぼ奈良田が 山がであれど
住めば都の花が咲く
お湯へ来たなら 奈良田の里へ
奈良田七段七不思議(月刊山梨記載)
奈良田の人口は57人(世帯数35)平成12年の調査ですが、今はもっと少なく
なっているかも知れません。交通の便が悪く、車を運転できない私には行く術があり
ません。奈良田の村を「奈良の都」と結びつける奈良王様の伝説があり、その出所は
相当古いものではないか、とも言われています。
ねんねんころりよ おころりよ
坊やの寝たときゃ どこへ寝かしょ
奥の八畳の 真ん中へ
松が三本に 杉三本
合わせて六本 五葉の松
五葉の松より まだ可愛い
ねんねんよ ねんねんよ(甲府市屋形町)
大切に育てられれいる様子が読み取れます。
ねんねんころりよ おころりよ
坊やはよい子だ ねんねしな
寝えって起きたら 何ょやらっか
寝ればよい子だ 米のぼこ(赤子)
寝らねよたぼこ(悪い子) 麦のぼこ(中巨麗郡櫛形町)
ねんねこよ おさんねこよ
ねんねして起きたら なにをやらんじょう
酒桶けっからかして 酒飲ましょう
おねんこよ おねんねこよ
よい子に寝たならご褒美に「酒飲ます」とは驚きですが、「おさんねこよ」「おね
んねこよ」との言い回しに、特異性が見られます。
============================================================================
◆コラム−上杉鷹山(うえすぎようざん)
「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」深い意味を
持ったこの言葉の提唱者が上杉鷹山であったということや、彼がどのような人物であ
ったかも知りませんでした。
1751年、宮崎県の高鍋藩主の次男として生まれ、10歳で米沢藩主上杉重定の
養子になりました。テレビドラマ「天地人」のあの上杉家です。17歳で9代目藩主
となり、35歳で治広(重定の子)に家督を譲った時に「伝国の辞」と呼ばれる家訓
を贈りました。「自助・互助・扶助」の精神が込められています。
多くの事業の中で感心させられたことは福祉のことです。この時代には間引き(堕
胎)が多くありました。避妊知識もなく、子どもを生んでも育てられない貧しい庶民
を救うため育児資金を捻出しました。それによって米沢藩において堕胎間引きはなく
なったと言うことです。また、働けなくなった老人を、口減らしのために野山に捨て
ていた悪習も、70歳以上の老人は村で責任を持って世話をすることを決め、自らも
敬老養老を実践したと言うことです。現代に欲しい政治家です。
============================================================================
◆編集後記
10日ほど前、昇仙峡に行ってきました。紅葉にはまだ少し早かったのですが、気
持ちのいい景色でした。鮮やかに色付いた柿が目に留まり、買ってきました。食欲の
秋と言われている通り、体重のコントロールに苦労する私です。wiiフイットを始
めて2ヶ月になりますが、コメントはいつも「目標に向けて頑張りましょう」です。
先日植えた水仙がもう芽を出してきました。上手く咲いてくれるでしょうか。金の
鈴、楽しみです。
============================================================================
このメールの配信を今後希望されない方は、お手数ですが、次のURLから配信中止の
手続きをお願いします。
http://komoriuta.cside.com/nenneko/koudoku.html
----------------------------------------------------------------------------
●子守唄研究室
・ホームページアドレス
http://komoriuta.cside.com/
・メールアドレス
komoriuta@cside.com
============================================================================
<<次の号 前の号>>


|