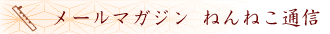

タイトル:ねんねこ通信30号
日付:2008/2/24(日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ねんねこ通信 30号 2008.2 http://komoriuta.cside.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎目次
●後期高齢者医療制度
●季節の行事(雛祭り)
●コラム−桃の節句
●編集後記
============================================================================
◆後期高齢者医療制度
この制度の内容についてはあまり知らされていませんが、この4月から施行されま
す。簡単に言えば、75歳以上の人は現行の健康保険の対象からはずされて、高齢者
だけの医療制度(保険ではありません)に組み込まれるということです。
今まで子供の扶養家族としてその会社などの健康保険の被保険者となっていた人も、
今度は自分で保険料?を支払うことになります。年金から差し引かれるのでしょうか。
この年齢になっている知人は「戦争では、国のために死ねと言われ、今度は、病気
になったら死ね、と言うのか!」と憤っていました。
以前話題になった「かかりつけ医」や「担当医」のことや、診療所か大病院かなど
問題は山積のままの、見切り発車のような気がしてなりません。
============================================================================
◆季節の行事(雛祭り)
おらが嬢やは いつ生まれた
三月桜の咲くときに
それでお顔が桜いろ
ねんねしてくれ お鼻がなる
お鼻のなる子は 可愛いもの (千葉県)
坊やはよい子だ ねんねしな
ねんころねんころ ねんころよ
坊やはお寺に連れられて
どこに遊ぶが お好きだね
春は羽根つき 紙鳶(タコ)遊び
梅や桜の花の下
桃の節句になったなら 白酒あげよか雛の前
菖蒲月には柏餅 夏は七夕星祭り
すすき団子は月の夜 色も香もよい菊の花
お餅つく音聞きながら 坊やの待つはお正月 (静岡県)
坊ちゃんはお守りにつれられて
どこに遊ぶがお好きだろ
春は羽根つき凧遊び
梅や桜の花のもと
桃の節句になったらば
白酒あげよか雛の前
夏は甘茶を釈迦の前
菖蒲 七夕 柏餅
天王さまのお神輿に
わいわいさわぐもうれしかろ (群馬県)
お盆がすんだらお正月
勝沼さんより武田武士
菱より三月雛まつり
祭万燈 山車 屋台
鯛に 平目に 蛸 まぐろ
ロンドン異国は大港
登山するのが お富士さん
三遍回って煙草にしょ (東京都)
「雛祭り」がうたわれている子守唄を探してみたのですが、今のところ3つしか見
つかりませんでした。「嬢や」と女の子を主人公にした唄も少ないので、仕方がない
のかもしれません。そして「嬢や」より「坊や」の方が唄いやすいのも確かです。
静岡と群馬の唄は、内容が似ていますが、東京都の唄は、言葉遊びのような観もあ
ります。
=============================================================================
◆コラム−桃の節句
私の誕生日は3月2日です。物心ついた時から人形(特に雛人形)への関心が強く
ありました。3月3日は五節句のひとつで「桃の節句」とも言います。
平安時代の公家社会に「雛遊び」といった人形で遊ぶ「ままごと遊び」のようなこ
とが行われていました。源氏物語や枕草子の中に「雛遊び」のことが書かれています。
この季節に咲く花には梅や桃がありますが「桃」が選ばれた理由は、古事記や日本
書紀に由来していると言われています。
古事記の「黄泉の国」の項に、死んだ妻(イザナミの命)をイザナギの命が迎えに
行き、連れ戻そうとしますが不可能であることを知り、逃げ帰ります。その時黄泉の
国の亡霊が追って来るのですが、彼は自分の持ち物を投げて気をそらせ逃げ続けます。
あの世とこの世の境界に来たとき、そこにある桃の木から実を3つとって投げました。
すると亡霊はことごとく逃げて行った、のだそうです。桃の実が悪霊を払うという中
国思想に基づいていると注に書いてありました。(古事記−岩波文庫−倉野憲司校注)
============================================================================
◆編集後記
1月30日午後、私の母は98歳6ヶ月の人生の終焉を迎えてしまいました。とて
も元気でしたので百歳以上は生きるはずだと、本人も自覚していて、白寿のお祝いを
楽しみにしていたのです。たった半日の入院で、眠るように夫のもとに行ってしまい
ました。母は宮崎から上京し、働きながら夜学に通い、当時、女性の花形の職業だっ
た観光バスガイドとして働いていたのです。関東大震災も戦争大戦も生き延びてきた、
明治・大正・昭和・平成を生きた女性のたくましさを具えた人でした。
その母も晩年は、思うように動かなくなった身体のことを嘆いていました。話し相
手もいなくなって寂しがっていたのに、もっと母のもとに通って、話し相手になって
やればよかった、と。今さら遅いけれど、ごめんね、おかあさん。
============================================================================
このメールの配信を今後希望されない方は、お手数ですが、次のURLから配信中止の
手続きをお願いします。
http://komoriuta.cside.com/nenneko/koudoku.html
----------------------------------------------------------------------------
●子守唄研究室
・ホームページアドレス
http://komoriuta.cside.com/
・メールアドレス
komoriuta@cside.com
============================================================================
<<次の号 前の号>>


|