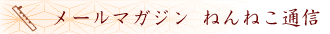

タイトル:ねんねこ通信22号
日付:2007/2/4(日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ねんねこ通信 22号 2007.2 http://komoriuta.cside.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎目次
●女性は子どもを産む機械?
●宮崎県の子守唄
●コラムー日本人は何を食べてきたのか
●編集後記
============================================================================
◆女性は子どもを産む機械?
厚生労働大臣が人権を無視したような発言をして、社会を騒がせています。どのよ
うな発想からあのような言葉が出てきたのでしょうか。責任ある立場の人が公の場所
でする発言とは思えない言葉です。以前、石原都知事が対談の中で「子どもを産めな
くなった(年齢の)女性は用なしである・・・」とか言うような話をしたということ
で女性達から抗議の嵐を受けたことがありました。
不用意に口にしてしまう言葉を、潜在意識にその考えを持っているからだと責める
ことは出来ませんが、「火のないところに煙は立たない」と昔から言われているよう
に、柳原大臣の本心はいかがなものだったのでしょうか。
安心して子育ての出来る社会を作るのが、責任ある立場にいる人達の役目です。機
械には心がありません。心がなければ子育ては出来ないのです。
============================================================================
◆宮崎県の子守唄
今、宮崎県は知事や鳥インフルエンザのことなどで、何かと話題になっています。
私の母は明治42年7月生れ、誕生日がくれば98歳になります。宮崎県西諸県郡
高原タカハル町の農家に生れました。その町でうたわれていた子守唄です。
ねんねねんねこ ねんねこよ
ねんねしなされ 夜がふけた
わたるそよ風 草の露
いったり来たり 夢の舟
親がうたえば 子がねむる
ねんねしなされ ねんねこよ (西諸県郡高原町)
けれども母が覚えている子守唄は
ねんねこ ねんねこ ねんねこよ
ねんねこ ねんねこ ねんねこよ
と、背負っている子のお尻を軽く叩きながら、抑揚をつけて繰り返してうたってい
たということでした。
ホーラホーラ ホーラヨ
ぼんがえんお父っちゃんな (坊やのうちのおとうさんは)
どこん行きやった (どこへ行ったのですか)
おかん先 焼酎飲んけ (通り道の先へ 焼酎のみに)
焼酎飲んで 酔イくろうて (焼酎飲んで 酔っ払って)
正月どんの べんじょを 汚らけて (お正月の晴れ着を汚したので)
むらざけ川で 洗やったどん (村境の川で洗ったけれども)
干すとこがなくて 草っ原へ (干すところがなくて 草原へ)
干しちょきやったら のっがいって (干しておいたら野火があって)
ひん燃えっしもっ ちょっしもた (燃えてしまった しまった)
ホーラホーラ ホーラヨ (都城市太郎坊)
都城は焼酎の本場です。
むかえの原に 鹿が鳴く
さびしゅて鳴くか 妻呼ぶか
さびしゅて泣かぬ 妻呼ばぬ
あすはこの山 狩がある
ここらは狭まし 子は多し
逃げよとすれば 子が惜しゅし
助けたまえよ 山の神
助けたもうた お礼には
四角四面の 堂たてて
石の燈籠に 火を明かす (児島郡西米良村村所)
鹿の鳴き声に思いを寄せる村の人の心をうたっていますが、意味を汲み取ると、こ
の狭い土地に暮らしてきた米良の人達の気持ちが、子煩悩な鹿にことよせてうたわれ
ているようでもあります。
少しかわった唄を紹介します。
・ねんねんこまり ねんこまり
坊やがお父さんどこへ行た
海山越えて里越えて
坊やがお土産に鬼の首
お父さんはたくましく強い人の象徴なのでしょうか。めったに手にすることの出来
ない物をお土産に持って帰ってくるのですから。
・よいよいよいと ねる子はかわい
起けて泣く子の つらにくさ
こげな泣く子は あぶらげに揚げて
となり近所の お茶じょうけ(お茶うけ)
守り子唄に分類されている唄です。昔から「泣く子と地頭には勝てぬ」といわれて
いるように、幼い子守りには辛い仕事でした。
=============================================================================
コラムー日本人は何を食べてきたのか
「食」については以前から関心があって、本屋さんに立ち寄っては物色していて、
この本に出会いました。タイトルに目を引かれて手にとって見ると、表紙には藁筒の
納豆の写真がありました。いま何かと話題になっている納豆ですが・・・。
第1章−日本人は何を食べてきたのか−に始まり、2章−米の源流をたどる、3章
−調味料の文化史、4章−食べ方の系譜、5章−台所道具のルーツ、6章−「食」の
しきたりまで、興味をそそられることばかりでした。
プロローグ「縄文時代の華やかな食生活」に、クリ・クルミ・ドングリ・シイ・ト
チなどの木の実を、石皿とすり石を使ってすりぶして粉にし、それに水を加えて練っ
て、パンやクッキーのようなものを作っていたと書かれていました。
縄文人もけっこうなグルメだったのですね。
書名「日本人は何を食べてきたのか」永山久夫監修 青春出版社
===========================================================================
編集後記
暫くご無沙汰してしまいました。実はあるビジネスコンテストに応募するための準
備に、時間を取られていたのです。それが一次審査をパスし、2次審査のプレゼンテ
ーションの準備をし、審査の結果「審査員奨励賞」を受けました。3月にその表彰式
があるのですが、その企画を実施するための資金をどのようにして集めようかと、今
から頭を悩ませています。
でもこれも何かのチャンスですので、チャレンジしてみます。
表彰式が終わったら、企画の内容をお話します。アイディアを下さい。
============================================================================
このメールの配信を今後希望されない方は、お手数ですが、次のURLから配信
中止の手続きをお願いします。
http://komoriuta.cside.com/nenneko/koudoku.html
----------------------------------------------------------------------------
●子守唄研究室
・ホームページアドレス
http://komoriuta.cside.com/
・メールアドレス
komoriuta@cside.com
============================================================================
<<次の号 前の号>>


|