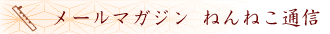

タイトル:ねんねこ通信129号
日付:2024/8/24(土)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ねんねこ通信 129号 2024.8 http://komoriuta.cside.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎目次
●日本の人口
●各地の民話から(沖縄県)
●コラム―近現代日本の家族形成と出生児数−子どもの数を決めてきたものは何か
●編集後記
============================================================================
◆日本の人口
総務省は、住民基本台帳に基づく今年1月1日時点の人口を、1億2156万1801人と
発表しました。前年より86万1237人の減少です。出生数と死亡数の自然増減は85万人
超で、1979年の調査開始以降最大の減少です。年代別に人口に占める割合は(概算)
15歳未満11%、15〜64歳57%、65歳以上32%(そのうち75歳以上19%、85歳以上
7%)となっています。
世界の全人口は81億1900万人で、前年より7400万人の増です。1位はインドで14億
4170万人、2位は中国で14億2520万人、3位はアメリカで3億4180万人、次にインド
ネシア、パキスタンと続きますが、インドと中国で世界人口の35%以上を占めていま
す。世界の人口は前年より7400万人増です。この先、食糧事情や難民問題が気になり
ます。争い事を起こしている場合ではないように思われます。
============================================================================
◆各地の民話から(沖縄県)
七つ星の娘
昔 あるところにとても貧乏な親子が住んでいました。息子は親思いで心の優しい
人でしたが、貧乏なためお嫁さんに来る人がいません。そんな息子のようすを天に輝
く七つ星の一番上の娘が見ていました。ある晩、その娘は羽衣をまとって地上に降り
男の帰りを待っていました。男は不審に思い、別の道に行くと、またそこにも娘がい
るのです。娘は「あなたのお嫁さんにしてください」と頼みましたが、男は「とても
貧乏なので、あなたのような美しい人をお嫁さんにはできません」と断りましたが、
娘は男の後を追いかけてきて、お嫁さんになりました。やがて男の子が生まれ、幸せ
な毎日を過ごしていました。
そのころ、天のお城で星の数を調べていた役人が、七つ星の一ばん上の星が消えて
いることに気付き、王様に知らせました。王様はすぐに探しだすように命じ、役人は
あちこち探しまわって娘を見つけ出しました。「明日の晩、連れて帰るので、用意し
ておきなさい」といって帰っていきました。あくる日の夜、娘は羽衣をまとい、寝て
いる子どもに今までの事情を話しかけ、許しを請うて天に戻っていきました。ところ
が天の入り口が見えてくると、子どものことが気になり、地上に戻り子どもを抱いて
天に舞い上がりました。「私は地上で結婚し人間として暮らしてきた星ですから、一
ばん上で輝くことは許されません」といって二ばん目で輝くようになりました。それ
で北斗七星の二ばん目の星のそばには小さな星がかすかに光っているのだそうです。
参考図書 (沖縄の由来ばなし―要約) 沖縄文化社
母アンマーがよ
母アンマーがよ 飛び衣やよ (お母さんがね 羽衣を)
六股ぬよ 八股ぬよ (六つ股の八股の)
倉ぬしたねー 隠ちぇーくとゥよ (高倉の下へ隠すよ)
誰に着しゅらん (誰にも着せないよ)
汝にる着しゅる (お前にだけ着せるよ)
ホイヨーホイヨー 泣かんぐとゥーし ねんねしよ
ホイヨーホイヨー 泣かんぐとゥーし ねんねしよ
※銘苅子メカルシという百姓が、畑からの帰りに小川で水浴する美しい女性に魅せられ
て松の枝にかけてあった羽衣を隠してしまい、その美女を家に連れて帰って妻にし
てしまう。二人の子供が生まれ、九つになった娘が五つの弟の守りをしているとき
に「羽衣は倉の稲束の下にあるから泣かないで、羽衣をあげるから」とうたってい
るの聞いて、母親は天の掟に従って天女となり、子ども達を置いて天に帰った。
※民話の話では、自分から進んで結婚した。子守唄の話では無理やり結婚させられ
なっています。そこで子どもを想う気持ちが違ってくるのでしょうか。
============================================================================
◆コラム―近現代日本の家族形成と出生児数−子どもの数を決めてきたものは何か
大変多くの資料から調査されている著書ですが、私は副題に書かれている「子ども
の数を決めてきたものは何か」が気になり、その副題を中心に読み解いて見ました。
明治前期の人口に関する国家政策は、徴兵制と人口政策で、富国強兵を目指し国民
皆兵による軍隊編成のため、兵士となる者を増やすべく人口増加政策を取りました。
1873年に徴兵令を公布し、士族・平民を問わず、満20歳に達した男子はすべて兵籍に
入ることを義務づけました(ある条件によっては免除あり)。
戦時期の人口増加政策では「産めよ増やせよ国の為」のスローガンのもと、各地に
公立の「結婚相談所」や「公営媒介所」が開設されたり、民間の「結婚斡旋所」など
も作られたり、このスローガンは全国的に流布されました。(中略)
少子化問題を労働問題と捉え、男女未婚率の高さは個人の意思でなく社会問題であ
ると言っています。庶民は、家族の生活を確保できるようになって結婚した。そうや
って生きようと思っても、結婚できないような社会に変えられ、子どもの数は減るば
かりという社会になろうとしている。
最後に著者は「若者が近現代の歴史を見返して、今、自分たちがどういう社会に生
きているのかを考える一助になってくれることを願う」と言っています。
参考図書 近現代日本の家族形成と出生児数 石崎昇子著 明石書店
============================================================================
◆編集後記
暑い日が続いています。40度を超える都市も数多くありました。風呂の温度を40度
前後に設定しているお宅も多いと思いますが、その暑い空気がずっと体にまつわりつ
いていると想像するだけで気が変になります。
8月15日は79回目の終戦記念日でした。日本は戦後の処理をどのようにしたのか、
何か曖昧にしてきたように思えてなりません。戦犯を裁いただけで良かったのでしょ
うか。個人を責めるわけではありませんが、国として何か足りない気がしてなりませ
ん。新たな資料が報道され、隠れていた事実が明らかにされてきました。軍部に忖度
していなかったでしょうか。国民は「死に損」ではすまされません。
月桃が咲きました。この暑さで目覚めたのでしょう。
============================================================================
このメールの配信を今後希望されない方は、お手数ですが、次のURLから配信中止の
手続きをお願いします。
http://komoriuta.cside.com/nenneko/koudoku.html
----------------------------------------------------------------------------
●子守唄研究室
・ホームページアドレス
http://komoriuta.cside.com/
・メールアドレス
komoriuta@cside.com
============================================================================
<<次の号 前の号>>


|