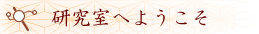

子守唄について
 子守唄のはじまり - 唄はどのような時に口ずさまれるか - 子守唄のはじまり - 唄はどのような時に口ずさまれるか -
 子守唄の分類 - 「ねむらせ唄」「遊ばせ唄」「守り子唄」 - 子守唄の分類 - 「ねむらせ唄」「遊ばせ唄」「守り子唄」 -

 子守唄のはじまり 子守唄のはじまり
子供を育てるとき、いつの頃から唄をうたうようになったのでしょうか。
資料の中から探してみました。
平安時代に書かれた日記や物語などから子育てを探ってみると、何時の時代にも子育てが大変であったことがうかがわれます。身分の高い家では、母親は自分で子育てはせず、すべて乳母(メノト)とよばれた女性がしていました。
清少納言の枕草子に『苦しげなるもの、夜泣きといふものするちごの乳母』(161段)とあります。「夜泣きをしている子どもをお守りしている乳母は、なんて大変でご苦労様なことよ」と傍観者の立場で書いています。中世の公家や武家において、幼児の養育にあたっていたのは乳母でした。
子守唄として文献に残されているものでは、1772年に刊行された民謡集「山家鳥虫歌」に、【勤めしょうとも子守はいやよ お主にゃ叱られ子にゃせがまれて 間に無き名を立てられる】(志摩地方)とあります。この頃から労働としての守り子が現れ、子守奉公と守り子唄が歌われ始めたのであろうと見ることが出来ます。
また、釈行智著「童謡集」(1802年)には、江戸子守唄の典型といわれている「寝させ唄」が書かれています。
ねエゝんね〜んねんねこよ。ねんねのおもりはど〜こいたア。
や〜まをこ〜えてさ〜といて〜。さ〜との御みやに名にもろた〜。
でんでん太鼓に笙のふえ〜。おきあがりこぼしにふりづヾみ〜。
ね〜ゑんね〜ゑん。ねんころり。
ころころや〜まのう〜さぎは〜。な〜ぜにお耳がなご御ざる〜。
お〜やのおなかにゐる時に〜。びわの葉た〜べてなご御ざる〜。
あ〜すはとうからおひんなれ〜。あ〜かのまんまにとゝそえて〜。
ざ〜んぶざんぶとあげましよよ。ね〜ゑんね〜ゑんねんねこよ〜。


|