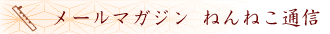

タイトル:ねんねこ通信33号
日付:2008/9/4(木)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ねんねこ通信 33号 2008.9 http://komoriuta.cside.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎目次
●エーデルワイス(西洋ウスユキソウ)
●ながい なが〜い 子守唄(京都)
●コラム−重陽の節句(9月9日)
●編集後記
============================================================================
◆エーデルワイス(西洋ウスユキソウ)
サウンド・オブ・ミュージックの中で歌われている「エーデルワイス」はあまりに
も有名ですが、実物の花を見ることが出来たのは7月のスイスの旅が初めてでした。
残念ながら自生しているものではなく、花壇で栽培されている花でしたが。
原産地はヨーロッパアルプス、シベリア、ヒマラヤ山脈などで、アジアからヨーロ
ッパにかけての標高1800〜3500mの日当たりのよい山岳地帯に分布していま
す。日本にも「ヒナウスユキソウ」など数種が自生しています。花期は7〜9月、
キク科の植物です。学名「レオントポディウム・アルピヌム」
花言葉は「尊い思い出」、8月18日の誕生花です。
エーデルワイスはドイツ語では「高貴な白い花」という意味だそうです。
============================================================================
◆ながい なが〜い 子守唄
優女(やしょうめ)、優女、京の町に、やしょうめ
売っつるものを見しょうめ、
防門町に売るもの、草毬唄(くさいがもち)はしろくて、
一口なれど調法(ちょうほう)、右京人の目の毒、
九条の町まで、あもと言うて通るは、すや殿のことかや、
店へ出いて置き売り、いただいて算(す)み売り、
山城の国から持って出て売るもの、
胡瓜、細根、白瓜、茄子(なすび)、瓠(ひしゃく)、氈瓜(かもうり)、
あこた瓜に、ほた瓜、唐瓜に姫瓜、
さこそ味のあるらめ、
菜売ろう、煮て売ろう、大根売ろう、
河骨蕪(かわほねかぶら)売ろう、蕗(ふき)売ろう、
おあえ召せという声、しおなくぞ聞こえて、
野老(とつころ)売らん、山の芋に里芋、
春の野にあるなる、かがみいずる早蕨(さわらび)
ゆきのひまにおせたる、つくづくし売ろうよ、
一もじすぎな、くくだち、浅葱(あさつき)も売ろうよ、
六角町に売るもの、売るもの、
鯉、鮒、鯛と鱸(すずき)と、比班魚(うぐい)、北目魚(かれい)、
鯰と、伊勢鯉と、鮨(なめし)と、螺(にし)や栄螺(さざえ)、
名吉(ぼら)の子、鮑(あわび)、鰹、スルメと、
正月に祝うは、柿や俵あいきょう、
ひしゃめはもち売り、鰆(さわら)の子は切り売り、
蛸の手も八つ、烏賊(いか)の手も八つ、乾蛸も売ろうよ、
防門町に売るもの、きんちょう、山鳥、山鴫(やましぎ)、田鴫(たしぎ)と
鶉(うずら)と、鵠(くぐい)、鴻(ひしくい)、雁と、鴨と、タカベと、
味は雀ちょうない、白小鳥も売ろうよ、
地獄の辻から、風が辻を見わたし、
室町を通れば、
売ろ売るまいは、上臈(じょうろう)さまの御ことか、
十七八から二十に余(あま)て、
二十四五の上臈、蓬蓬眉(ぼうぼうまい)に薄化粧、
はさきとって鉄黒(かねくろ)、立ちに立ちてまします、
我等がようなるあつなし、わたもいらぬすすあう、
せのひぼにきないて、紺の十徳、上にそっと着そうて、
杉形(すなり)の傘をばふかぶかと着そうて、
吹けど吹かねど尺八、腰についさし、
上臈さえの御側をよしよしとおた、
その時御上臈、袂(たもと)をじっと留めて、
御止まりあれや御殿とて、笑靨(えくぼ)はしおにあまった、
料足の一文、かたわれも持たねど、
男の義理なれば、まず御名を問うた、
これなる上臈の名をばなにと申し候、
はつはなと申し候、
春の初に面白や、はつはな、
これなる御上臈の名をばなにと申し候、
あたらし殿と申し候、あたらし殿と聞くより、
いまいでと思うてそと寄りて見たれば、
御名は新し、御顔は古う御りゃる、
さもあれ、かほどの御出ぞ、礼式のさぶろう、
礼式のこととは、一すじの御事か、思いもよらぬことなり、
われもさぶらわずば、ほうらく御連歌、
御連歌とは、五十文の御事か、思いも寄らぬことかや、
われさも候わずば伊勢への御まいり、
御まいりとはみわなりの御事かや、思いもよらぬことなり、
われさも候わずば、大名の御かど、
御かどとは五文(御門)のことかや、思いもよらぬことなり、
われさも候わずば御寺さまの御かど、
御かどとは三文(山門)のことかや、
時どきのあきないに、あれづるをれあしめ、えらしめ。(京都)
この唄の「注」に『蓮如上人の作といわれるが、真偽のほどはわからない』とあり
ました。終わりまで読んでいただけましたでしょうか。
表現が特異なので、書き写すのに苦労しました。
日本伝承童謡集成 第一巻 子守唄篇(編纂者 北原白秋)に採取蒐集されていま
す。初版は昭和22年6月、改定新版は昭和49年9月、発行です。
============================================================================
◆コラム−重陽(ちょうよう)の節句
重陽とは陽(奇数)が重なる日、奇数の中でも一番大きな数字という意味で、めで
たい日とされ、日本では奈良時代から宮中や寺院で菊を鑑賞する宴が行われていまし
た。菊の持っている独特の芳香から、邪気を祓い長生きする効能があると信じられて
きました。菊の花を浸したお酒を飲んだり、花をめでながら詩歌を読んだりして長寿
を祈ったと言われています。そのことから「菊の節句」とも言われます。
旧暦では秋の収穫が行われる時期でもあり、栗ご飯などで節句を祝ったりもしてい
ましたので「栗の節句」とも言われているようです。
暦にある五節句とは「人日(じんじつ)1月7日」「上巳(じょうし)3月3日」
「端午(たんご)5月5日」「七夕(たなばた)7月7日」「重陽9月9日」です。
============================================================================
◆編集後記
40年来の念願が叶って、スイスの山々をハイキングしてきました。天候にも恵ま
れ、美しいマッターホルン、凛々しいアイガー、奥ゆかしいユングフラウ、間近に迫
るベルニナアルプス、ちょっとだけフランスに行ってモンブランも、と贅沢な旅でし
た。しかし、ここにも温暖化の影響があるのか、氷河が年々後退しているそうです。
8月に駒ケ岳の千丈敷きカールを歩いてきました。スケールは違いましたが、根雪
も見られ山の景色を堪能してきました。
============================================================================
このメールの配信を今後希望されない方は、お手数ですが、次のURLから配信中止の
手続きをお願いします。
http://komoriuta.cside.com/nenneko/koudoku.html
----------------------------------------------------------------------------
●子守唄研究室
・ホームページアドレス
http://komoriuta.cside.com/
・メールアドレス
komoriuta@cside.com
============================================================================
<<次の号 前の号>>


|