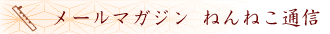

タイトル:ねんねこ通信126号
日付:2024/2/24(土)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ねんねこ通信 126号 2024.2 http://komoriuta.cside.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎目次
●確定申告
●五木の子守唄の謎
●コラム―言葉を探る
●編集後記
============================================================================
◆確定申告
2月16日の新聞に、国税庁からのお知らせが載っていました。「スマホ×マイナン
バーカード,e‐Taxが便利!」と。皆様はどのような気持ちでご覧になったでしょう
か。広辞苑によれば、確定申告「申告納税を行う場合に、納税義務者がその年の実績
に基づいて、所得金額とそれに対する税額とを計算し、源泉徴収額や予定納税額との
過不足を確定して申告納付すること」と書かれていました。事業者は良心にもとづき
収支決算をして、国民の義務である納税をしましょう…と言うことなのです。
今、メディアを騒がせている国会議員(主に自民党)の金銭感覚が国民には受け入
れられないようなズレがあります。収支報告書に記載しなくてもよい闇の金額が数億
円もあるとか。議員特権とでもいうのでしょうか、国民感情を逆なでするような愚策
を弄することはしないで欲しいと願っています。
今は確定申告書を提出する時期でもあります。
============================================================================
◆五木の子守唄の謎
♪おどま盆ぎり盆ぎり 盆から先きゃおらんど 盆が早よくりゃ 早よもどる
♪おどまかんじんかんじん あん人たちゃよか衆 よかしゃよか帯 よか着物
誰でもが知っている唄だと思いますが、謎の多い唄でもあります。この唄は人吉市
の小学校教師の田辺隆太郎氏によって、1930年にはじめて採集・採譜されたと言われ
ています。しかし。その当時、すでに五木村ではこの唄はほとんど歌われていなかっ
たらしいのです。その時採譜されたのは「五木地方の子守唄 二拍子」と「五木四
浦地方の子守唄 三拍子」でした。この隣り合う村において、歌詞は共有しながら
異質な旋律を持った子守唄が歌われていたのです。歌い手によっては、前半は三拍子
で後半は二拍子でうたうとかあり、歌詞の語数が関係しているとも考えられます。
戦後になって、この唄はNHKの電波に乗り、大量生産のレコード盤として販売さ
れ全国的に知られるようになりましたが、五木村で歌われてきた子守唄とは違ってい
ました。
五木村は平家の落人伝説をもつ山あいの村で、近世には五木三十三人衆と呼ばれる
地頭によって支配されていました。彼らダンナ衆が村内の土地のほとんどを所有し、
小作百姓がナゴ(名子)として隷属を強いられていました。そして、ナゴの娘たちは
口減らしのために奉公に出されていたのです。他の説では、一向宗の禁制に反発した
娘たちの抵抗が、五木の子守唄の発生を促したとする説、防人の唄とする説、乞食の
唄とする説、朝鮮戦役に駆り立てられた農民たちが望郷の念を歌ったという説、朝鮮
から連れてこられた陶工たちが望郷の思いをアリランの唄に託して唄っていたので、
子守たちがその旋律に近い唄をつくったという説、被差別部落の人々の唄とみなす説
など色々あります。どの説が正しいかと決めることは出来ません。唄われている歌詞
の中にそれぞれに当てはまる内容が見られるからです。(参考資料 赤坂憲雄著
子守唄の誕生−五木の子守唄をめぐる精神史‐講談社現代新書 KICG3078
五木の子守唄の謎−CDです)
高村逸枝の「女性の歴史」の中に、五木の子守唄に触れた一節があります。
屈辱時代の終焉への花束として、熊本五木の子守歌をささげたい。女の動く日は山
の動く日であるという。女のなかでも、もっとも下積みの女であるとされた江戸封建
期の子守娘たち。その彼女たちが血を吐くおもいで歌いあげた歌のかずかずは、一八
世紀以後の百姓一揆や都市細民の打ちこわし等にみられたあのものすごかった時代の
うごきと、おそらくは命脈をおなじくするものだったろう。
この歌は五木のもでなく、肥後一円で歌われた。私は熊本南部の水田地帯に育った
が、10,20人とうち群れて、肥後の大平野をあかあかと染めている夕焼けの中で
この歌を声高く合唱する子守たちのなかに私もよくまじっていた。ただし、歌詞は、
平地から山地へと入るにしたがって深刻となり、球磨の五木へんで絶頂にたっしてい
たとおもう。そのわけは、後にいうように、そのへんが子守たちの大量給源地であっ
たからだろう。
♪おどまくゎんじんくゎんじんあのしたちゃよかし よかしゃよか帯よか着もん
♪おどま馬鹿々々馬鹿のもった子じゃで よろしゅ頼ンます利口リクか人
熊本地方では、くゎんじんと馬鹿の二つが、ののしりことばの極致とされた。この
二つが人間の最下層とされた。この歌には、この最下層を自任する一群の子守娘たち
が、他のそうでない階層に対立して、戦闘開始を宣言している姿がみられる。
参考図書(高村逸枝著 女性の歴史(上)講談社文庫)
次回は手持ちの資料にある歌詞をすべて紹介します。
============================================================================
◆コラム―言葉を探る
人と話をしていて「あれ?何か変!どおして?」と思わず絶句してしまって経験が
あります。私の話し方が悪かったのだとは思いますが、相手に正しく伝わっていなか
ったのです。どこにずれがあったのか、はじめから説明をし直しました。
言葉は、思考する・表現する・伝達する・記録することに使われます。思考した事
柄を言葉にする時、その内容にピタリと当てはまる言葉がなかなか見つからないこと
があります。語彙力や知識の不足は認めますが、何かモヤモヤとしたアノことが言葉
に表現できなくて時間を費やしたことがしばしばありました。今も・・・です。その
時浮かんだ言葉は、先に進むための妥協の産物かもしれませんが、間違えではないこ
とは確かです。言葉について、その言葉で説明することは難しいですね。
古今和歌集仮名序に『やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれり
ける。世の中にある人、事業コトワザ、繁きものなれば、心に思うことを、見るもの聞
くものにつけて、言ひだせるなり。・・・・』とありました。詠み人の心情を表現す
る道具であり、そう「言の葉」なのです。樹木に例えれば、落葉樹は毎年新芽をうみ
だし、常緑樹は年毎に枝葉を茂らせます。仮名序は紀貫之が書いたとされています。
============================================================================
◆編集後記
今回、言葉について書こうとした時、表題に迷い、内容に迷い、何を伝えたいのか
さえ決めかねていたのです。「でも、言葉について書きたい」以前から考えていたこ
とですが、やはり上手く書けませんでした。「言の葉」という言葉に巡りあった時、
「ああ、これだ」と思いました。
世界中で戦闘が激化しています。戦禍に惑う人々の姿を見ると胸が痛みます。何が
このような行動を引き起こさせるのでしょうか。「命」ほど尊いものはありません。
============================================================================
このメールの配信を今後希望されない方は、お手数ですが、次のURLから配信中止の
手続きをお願いします。
http://komoriuta.cside.com/nenneko/koudoku.html
----------------------------------------------------------------------------
●子守唄研究室
・ホームページアドレス
http://komoriuta.cside.com/
・メールアドレス
komoriuta@cside.com
============================================================================
<<次の号 前の号>>


|